うつ病
このようなお悩みはございませんか?
- 毎日憂鬱で、何をするにもやる気が出ない
- 何をしても楽しく感じられなくなった
- 周りの人との会話が億劫になり、孤立しがち
- 食欲不振で、いつもお腹がすかない
- 不眠で夜なかなか寝付けない
- 眠っても熟睡できず、疲れが取れない
- 仕事や勉強に集中できず、ミスが増える
- 自分が悪いと思い込み、自己嫌悪に陥る
うつ病とは
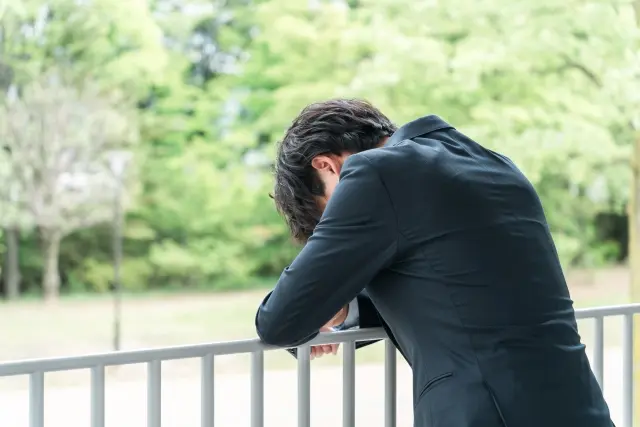
うつ病は、深い悲しみや無力感に長く悩まされる病気です。
日常生活に支障が出るほどの強い疲労感や、生きる希望を失ってしまうこともあります。
多くの人に知られるようになってきましたが、依然として誤解されている部分も多く、適切な治療を受けられないケースも少なくありません。
うつ病の正しい知識を持つことは、早期発見・早期治療につながり、回復を早めることにつながります。
うつ病で見られる症状
うつ病の症状には「精神症状」と「身体症状」の2つに分けられますが、個人差があります。
【精神症状】
うつ病の精神症状には、下記のようなものがあります。
抑うつ気分
精神症状の中でも代表的なのが「抑うつ気分」です。
気分が落ち込み、精神的な不安定さや、憂うつ感、悲しさを感じるのが特徴です。
集中力や思考力の低下
集中力や思考力の低下により、物事をスムーズに進めることができず、日常生活や仕事に支障をきたすことがあります。
思考と行動の両方が鈍り、自信を失い、やる気をなくす悪循環に陥ります。
過度な自責感
心が重くなり、自己嫌悪に苦しんだり、未来に対しての希望を失い、どんな小さな失敗も必要以上に自分を責めるようになったりと、思考が悲観的になります。
意欲の喪失・低下
興味・関心の対象が狭まり、以前は楽しんでいた活動からも遠ざかってしまいます。
自己肯定感が低下し、外見にも無関心になり、日常生活に支障をきたすことがあります。
強い焦燥感
うつ病になると、何もないのに不安でたまらなくなることがあります。
体はだるいのに、心が落ち着かず、ソワソワして落ち着きがない状態が続くことがあります。
希死念慮・自殺企図
自殺を考えた人は、心の病を抱えていることが多く、その中でもうつ病が最も多い病気の一つです。
うつ病になると、「生きているのがつらい」「死にたい」といった漠然と死を願ったり、実際に自殺を図ろうとしたりすることがあります。
【身体症状】
うつ病の身体症状には、下記のようなものがあります。
睡眠障害
うつ病においては、睡眠障害を伴うことが多く、早朝覚醒、入眠困難、熟眠障害などが特徴的にみられます。
一方で、過眠がみられる場合もあります。睡眠障害による疲労蓄積は、精神的な安定性を損ない、うつ病の症状を悪化させます。
食欲の低下
食事の量が減り、栄養バランスが崩れることで、体力低下や体重の減少を招くこともあります。
一方で、衝動的な過食により体重増加を招く過食性障害を併発する場合もあります。
倦怠感・疲労感
うつ病になると、エネルギー代謝を低下させ、何をするにも疲れてしまい、体がだるく感じられます。
歯磨きや着替えといった簡単なことでも疲れてしまい、とても大きな負担に感じてしまいます。
さまざまな自律神経失調症状
体がだるくてやる気が出ないのに、逆に心臓がドキドキしたり、汗をかいたりすることもあります。
自律神経失調症状が現れ、頭痛、めまい、動悸、息切れなど、人によって異なる症状が複合的にみられます。
うつ病の種類
メランコリー型うつ病
一般的にイメージされる「典型的なうつ病」と言えるタイプです。メランコリーとは、一般的に憂鬱や悲しみを意味し、
メランコリー型うつ病は深い悲しみや絶望感、自己嫌悪といった特徴的な症状が現れます。
早朝覚醒や食欲不振、精神的な遅延といった身体的な症状も伴うことが多く、日常生活に大きな支障をきたします。
環境要因だけでなく、性格的な特徴や遺伝的な素因も発症に関与していると言われています。
非定型うつ病(新型うつ病)
「新型うつ病」と呼ばれることもある非定型うつ病は、普通のうつ病とは少し違う病気です。様々な要因が複雑に絡み合って発症する精神疾患です。
そのため、症状も人によって異なり、周囲に気づかれにくいケースも少なくありません。
性格的な特徴や遺伝的な背景に加え、日常生活での出来事が気分に大きく影響を与える「気分反応性」も、うつ病の特徴の一つとです。
過食や過眠、感情の起伏が激しくなるといった症状が現れることがあります。
周囲から「怠けている・甘えている」と思われがちですが、本人は強い孤独感や無力感に苦しみ、自己肯定感が著しく低下している状態です。
双極性障害(躁うつ病)
双極性障害は、躁うつ病とも呼ばれる病気で、うつ病とは異なる精神疾患です。
うつ病がいつも気分が落ち込んでいる状態なのに対して、双極性障害は、気分がすごく高揚したり、逆にすごく落ち込んだりする状態を繰り返します。
同じように気分が落ち込む病気ですが、最初の症状が似ていることが多いから、それがうつ病なのか、双極性障害なのかを見分けるのは簡単ではありません。
どちらの病気かによって、治療法が大きく変わるので、早めに専門医に相談することが大切です。
季節型うつ病
季節型うつ病は、季節の変わり目になると気分が落ち込む病気です。
特に、日が短くなる秋から冬にかけて、気分が憂鬱になったり、眠りすぎたり、いつもよりたくさん食べてしまう人がいます。
これは、太陽の光を浴びる時間が短くなることが原因の一つと考えられています。他にも、集中力が切れたり、何もやる気が起きないといった症状が出ることもあります。
産後うつ
産後うつは、出産後の女性がなる心の病気です。産後1年を過ぎてもなることもあります。
ホルモンバランスの変化や睡眠不足などで気分が落ち込んでしまう病気です。いつも泣いてばかりいたり、何もやる気が起きなかったり、赤ちゃんにあまり興味が持てないなど、さまざまな症状が現れます。
産後すぐの軽い気持ちの落ち込みである「マタニティブルー」とは違います。
仮面うつ病
仮面うつ病は、心の病気であるうつ病の一種ですが、心の症状よりも体がだるい、頭痛がするなど、体の不調が目立つ病気です。この病気は、遺伝や生活環境などの影響を受けて起こるとことが原因と考えられています。
頭痛や倦怠感、肩こり、お腹の痛みなどの体のあちこちに症状が現れます。精神症状が見えにくいことから、病名に仮面とつけられています。
うつ病の原因
うつ病の原因は、ひとつの原因で起こる病気ではなく、様々な要因が複雑に絡み合って発症します。
遺伝的な要因、脳内の神経伝達物質のバランスが崩れたり、ストレス、心理的なトラウマなど、多くの要因がうつ病の発症に関与しているとされています。
うつ病の治療法
うつ病治療の第一歩は、心身に十分な休養を与えることです。これに薬物療法や精神療法などを加えることでより効果的な治療が期待できます。
休養・環境調整
うつ病の治療には、十分な休養が不可欠です。そのためには、仕事時間の調整や家事の分担など、負担となるものを減らすため周囲の協力が大切です。
休養はうつ病回復への近道になります。
うつ病は、放置すると症状が長引く可能性があるので、早めに治療を始めることが大切です。
薬物治療
うつ病の治療では、十分な休養に加えて、薬も大切な役割を果たします。脳の働きをサポートする薬は、うつ病のつらい症状を和らげる効果が期待できます。
うつ病の治療では、基本としてSSRI、SNRI、NaSSAなどの抗うつ薬が中心となります。これらの薬は、脳内のセロトニンの量を増やし、うつ症状を改善します。
症状によっては、不安を鎮める抗不安薬や、睡眠の質を改善する睡眠薬などを併用することもあります。
精神療法
うつ病自体は休養と薬物治療で適切な治療により症状が改善し、元の生活に戻ることができます。
精神療法の中でも、認知行動療法や対人関係療法は、うつ病の再発予防に有効とされています。
患者さんに合わせて認知や行動パターンに焦点を当て、うつ病の維持・再発に関わる要因を軽減することを目指します。
治療の流れ
急性期:診断から3カ月程度
急性期は、気分の落ち込みや睡眠障害、食欲の低下などの症状が現れます。
うつ病の症状が悪化しやすく、十分な休養と薬物治療が特に効果的です。症状に合わせて、無理のない範囲で仕事を減らしたり、休職を検討したりすることも重要です。
必要であれば入院治療を行い、心身ともに休養できる環境を整えることも選択肢の一つです。周囲の理解とサポートが、回復への大きな力になります。
回復期:治療を開始してから4〜6カ月程度
うつ病の回復期は、症状が少しずつ改善していく大切な時期です。
この期間は、無理をしたり、焦って元の生活に戻ろうとせず、ゆっくりと体調を整えましょう。
調子が良くても、自己判断で治療を中断したり、無理なスケジュールを組んだりすると、症状が再発する可能性が高いため、必ず医師と相談しながら治療を続けることが必要です。
再発予防期:治療を開始してから1〜2年程度の期間
症状が安定し、社会復帰できるようになる方も増えてきます。
社会復帰に向けて、仕事や日常生活に少しずつ慣れていく中で、薬物治療も継続することが重要です。
薬を服用することで、気分の安定を図り、仕事や人間関係を円滑に進めることができます。
自己判断で薬を中止してしまうと、再び症状が悪化し、社会復帰が遅れてしまう可能性があります。主治医と相談しながら、薬物治療と社会復帰を両立させましょう。
